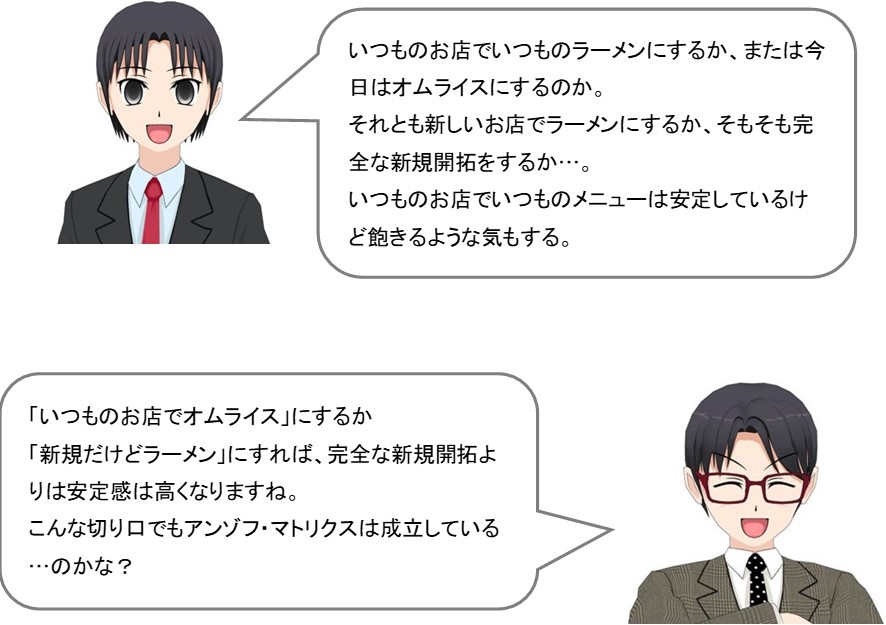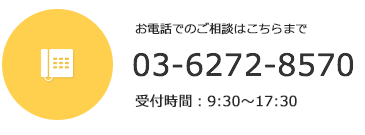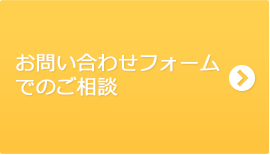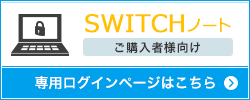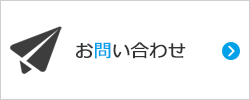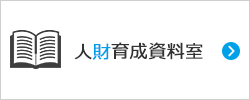HOME » 人財育成資料室 » 人材育成キーワード » 【イゴール・アンゾフ(人名)】
【イゴール・アンゾフ(人名)】
関連する研修⇒発想力研修、営業管理職対象 営業マネジメント研修、ソリューション営業力強化研修
ロシア系アメリカ人の経営学者、オペレーションズ・リサーチの研究者。
ドラッカー、チャンドラーと並び1950年代~60年代の経営学の黎明期を代表する経営学者の一人で、その功績から「真の経営戦略論の父」と呼ばれる。
1918年ロシアのウラジオストックに生まれる。
1936年にアメリカに移住し、スティーブンス工科大学で物理学の修士号、ブラウン大学で応用数学の博士号を取得する。
その後アメリカ陸軍航空軍が設立したシンクタンク「ランド研究所」で6年間働き、この時に「多くの組織は近視眼的になってしまう」「非継続的な戦略的変革には組織的な抵抗が起こる」といった今後の研究テーマともなる着眼点を得ている。
1957年にロッキード・エアクラフト社で企業計画部門、ロッキード・エレクトロニクス社で副社長になり、赤字部門を収益部門化する功績を上げる。
この頃から学術誌に主に多角化経営に関する論文を掲載し始め、1963年45歳でカーネギーメロン大学産業経営学大学院の教授に就任。
その後、1965年に「企業戦略論」1971年に「企業の多角化戦略」1979年に「戦略経営論」といった経営戦略の世界で非常に重要な著書を発表する。
「現状(as is)」と「あるべき姿(to be)」のギャップを分析する「ギャップアプローチ」や事業組織間で相乗効果を出す「シナジー」といった概念はアンゾフが最初に提唱したものである。
また、アンゾフ・マトリクス(下記)を提唱したことも重要な功績として知られている。
アンゾフは方向性の定まらない多角化経営を批判しながら「どうやって多角化するか、また組織間や事業間でシナジー発揮の方向性を見出すべきか」という問いへの回答となるツールとしてアンゾフ・マトリクスを作った。
その上で④の多角化経営はリスクが高いため最大限のシナジーを発揮できるように経営するべき、と説いた。
アンゾフは「戦略経営論」の中で外部環境の変化度合いに合わせて企業の組織も同じレベルで変化しなくてはならない、つまり「戦略だけが先に進んでも組織だけが先に進んでも失敗する」と説いた。
このメッセージは同時代のチャンドラーとの議論のようにも聞こえる上に、後の経営戦略論における「ケイパビリティ派」と「ポジショニング派」の対立の答えを先読みしたものと言える。
三谷宏治「経営戦略全史」より引用 筆者が一部加筆
関連するカテゴリーの記事
- 【社内運動会】
- 【配属ガチャ】
- 【モラール】
- 【課題対応研修】
- 【人材の見える化】
- 【ストレッチ・アサインメント】
- 【クロノロジー分析】
- 【アダプティブ・リーダーシップ】
- 【ガクチカ】
- 【インテグリティ・マネジメント】
- 【PLMシステム】
- 【エンプロイー・エクスペリエンス】
- 【Quiet Quitting】
- 【USP】
- 【マイクロラーニング】
- 【アンコンシャス・バイアス】
- 【マタイ効果】
- 【キャリア・ショック】
- 【管理職になりたくない症候群】
- 【イクメン】
- 【グラスシーリング】
- 【ウェルビーイング】
- 【カタリスト】
- 【行動科学】
- 【ペルソナ法】
- 【パーパス経営】
- 【アンカリング】
- 【ゲームニクス】
- 【ブレイクスルー思考】
- 【ピレネーの地図】
- 【ZOPA】
- 【現代型うつ病】
- 【センス・メイキング】
- 【BATNA】
- 【オーセンティック・リーダーシップ】
- 【働かないおじさん/おばさん問題】
- 【ファーム・スペシフィック・スキル】
- 【フェルト・リーダーシップ】
- 【社二病(社会人二年目病)】
- 【マインドフル・リスニング】
- 【マイクロマネジメント】
- 【アルムナイ・ネットワーク】
- 【ピープルマネジメント】
- 【セルフ・キャリアドック】
- 【ビッグファイブモデル】
- 【大退職時代】
- 【サプライチェーン・マネジメント】
- 【ソロモン・アッシュ(人名)】
- 【オフ・ボーディング】
- 【ジャーゴン】
- 【ファミリートレーニング】
- 【リーン・スタートアップ】
- 【SFBモデル】
- 【Woke Capitalism】
- 【氷河期世代】
- 【アウトサイド・イン思考】
- 【ジョブ・クラフティング】
- 【リフレーミング】
- 【ファスト教養】
- 【マシュマロ・テスト】
- 【MTP】
- 【ディーラーヘルプス】
- 【自己効力感(セルフエフィカシー)】
- 【TWI】
- 【権力の堕落(腐敗)】
- 【エビングハウスの忘却曲線】
- 【ロールモデル】
- 【オズボーンのチェックリスト】
- 【ゆるブラック企業】
- 【メタバース】
- 【クルト・レヴィン(人名)】
- 【ディズニーの3つの部屋】
- 【Z世代】
- 【QC活動】
- 【カルト】
- 【デマンド・ジェネレーション/リード・ジェネレーション】
- 【リスキリング】
- 【エドワード・ソーンダイク(人名)】
- 【アカウント・ベースド・マーケティング】
- 【セールスイネーブルメント】
- 【ハーバート・サイモン(人名)】
- 【チーミング】
- 【SFA】
- 【メーガーの3つの質問】
- 【ヒーローズ・ジャーニー(心理学用語)】
- 【NLP】
- 【ビジュアルシンキング】
- 【カスタマーサクセス】
- 【CRM】
- 【タイムパフォーマンス】
- 【インセンティブ】
- 【ゼークトの組織論】
- 【ジェネリックスキル】
- 【アルムナイ採用】
- 【リアリティショック】
- 【テストクロージング】
- 【BANT条件】
- 【レイクウォビゴン効果(心理学用語)】
- 【ポータブルスキル】
- 【コンピテンシー】
- 【社会人基礎力】
- 【シチュエーショナル・リーダーシップ理論(SL理論)】
- 【コブラ効果】
- 【ソリューション営業】
- 【ベンチマーキング】
- 【アイスブレイク】
- 【ロバート・ミルズ・ガニエ(人名)】
- 【経験学習理論】
- 【ピア・ラーニング】
- 【ティール組織】
- 【トータル・リワード】
- 【トーマス・J・ピーターズ(人名)】
- 【ジャスパー教材設計7原則】
- 【アンカード・インストラクション】
- 【フレッド・グラック(人名)】
- 【サイロ・エフェクト】
- 【マイケル・ポーター(人名)】
- 【カークパトリックモデル】
- 【アンラーニング】
- 【ドア・イン・ザ・フェイス・テクニック】
- 【ダニエル・カーネマン(人名)】
- 【アンドラゴジー】
- 【HPI】
- 【ジグソーメソッド】
- 【ブルース・ヘンダーソン(人名)】
- 【プロジェクトマネジメント】
- 【デール・カーネギー(人名)】
- 【CLO】
- 【組織開発】
- 【(組織の)心理的安全性】
- 【ハインリッヒの法則】
- 【マーヴィン・バウアー(人名)】
- 【ARCSモデル】
- 【エコーチェンバー効果(心理学用語)】
- 【ケネス・アンドルーズ(人名)】
- 【デザイン思考】
- 【意識高い系】
- 【チェスター・バーナード(人名)】
- 【集団思考/集団浅慮(心理学用語)】
- 【応酬話法】
- 【ダグラス・マクレガー(人名)】
- 【エンパワーメント】
- 【反知性主義】
- 【ロックダウン世代】
- 【ジョハリの窓(心理学用語)】
- 【フット・イン・ザ・ドア・テクニック】
- 【ブラック企業】
- 【クレイトン・クリステンセン(人名)】
- 【ダブルループラーニング理論】
- 【アイゼンハワーマトリクス】
- 【AIDMA(アイドマ)の法則】
- 【クリス・アージリス(人名)】
- 【システム思考】
- 【二要因理論(心理学用語)】
- 【1on1ミーティング(ワンオンワンミーティング)】
- 【六次の隔たり】
- 【野中郁次郎(人名)】
- 【マネジリアルグリッド理論】
- 【ノルマ】
- 【アンリ・ファヨール(フェイヨール)(人名)】
- 【人間関係論】
- 【リフレクション】
- 【能力主義】
- 【コーポレート・アイデンティティ】
- 【アルフレッド・デュポン・チャンドラー(人名)】
- 【マインドフルネス】
- 【セレンディピティ】
- 【アクティブ・ラーニング】
- 【ファシリテーション】
- 【オンライン研修/リモート研修/web研修】
- 【バランスト・スコアカード】
- 【成功の循環モデル】
- 【イゴール・アンゾフ(人名)】
- 【アクションラーニング】
- 【プランド・ハプスタンス・セオリー】
- 【エンプロイアビリティ】
- 【MBO】
- 【リベラル・アーツ】
- 【コーチング】
- 【テレハラ/リモハラ】
- 【フィリップ・コトラー(人名)】
- 【SDGs】
- 【アサーション】
- 【ピーター・ファーディナント・ドラッカー(人名)】
- 【リテンション】
- 【競争の型】
- 【レジリエンス(心理学用語)】
- 【ストーリーテリング】
- 【SPIN話法】
- 【階層別教育】
- 【カッツモデル】
- 【フォロワーシップ】
- 【メンバーシップ型採用】
- 【解決志向アプローチ(ソリューションフォーカスト・アプローチ)】
- 【タレントマネジメント】
- 【学習する組織】
- 【パワーハラスメント】
- 【ジョブ型採用】
- 【アブラハム・マズロー(人名)】
- 【コンプライアンス】
- 【ソーシャルビジネス】
- 【ザイアンスの法則(心理学用語)】
- 【メラビアンの法則(心理学用語)】
- 【コア・コンピタンス】
- 【アンダーマイニング効果(心理学用語)】
- 【ワールドカフェ】
- 【リンゲルマン効果(心理学用語)】
- 【メンター】
- 【カスタマー・ハラスメント】
- 【オリエンテーション】
- 【グループ討議】
- 【ケーススタディ】
- 【インバスケット】
- 【ジョージ・エルトン・メイヨー(人名)】
- 【OODAループ】
- 【終身雇用制度】
- 【オン・ボーディング】
- 【ハラスメント】
- 【ロジカルシンキング】
- 【職能教育】
- 【自己成就予言(心理学用語)】
- 【ダイバーシティ】
- 【センシティビティ・トレーニング】
- 【キャリア・オーナーシップ】
- 【プロテウス効果(心理学用語)】
- 【ハロー効果(心理学用語)】
- 【水平的評価】
- 【垂直的評価】
- 【成果主義(インストラクショナルデザイン)】
- 【インストラクショナルデザイン】
- 【エンゲージメント】
- 【リファラル採用】
- 【グッドウィル活動】
- 【ロールプレイング】
- 【クロージング活動】
- 【プロポーザル活動】
- 【リサーチ活動】
- 【アプローチ活動】
- 【ウイリアム・エドワード・デミング(人名)】
- 【オペレーションズ・リサーチ】
- 【CS】
- 【ヘンリー・ローレンス・ガント(人名)】
- 【フランク・バンカー・ギルブレス(人名)】
- 【フレデリック・テイラー(人名)】
- 【KKD】
- 【OJT】
- 【IE】
- 【チャレンジャーセールス】
- 【ゲーミフィケーション】