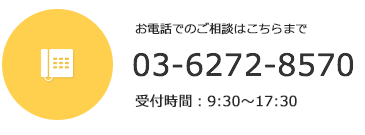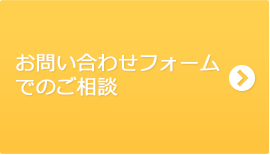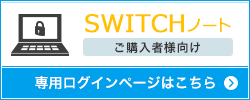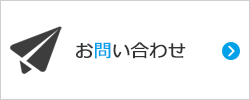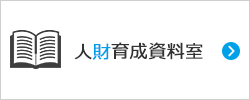HOME » 人財育成資料室 » 管理職実践講座 » 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)③
11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)③
3.パワハラへの自覚がない人の思考傾向
パワハラ行為をしているにもかかわらず、その自覚がない管理職も相当数に上っています。こうした管理職には共通的な思考の傾向があるようです。
①「昔の価値観」をそのまま引きずっている
今や「昭和の時代の価値観」と揶揄されるようなことですが、「昔はこうだった」「私は若い時このように指導されて育ってきた」などで、指導には厳しさが必要という考えを根強く持っています。そのため、部下がどう受けとめているかはあまり気にせず、自分が正しいと思う指導に終始してしまいます。そして時に、「やる気がないならやめろ」などの高圧的な言葉が飛び出してしまいます。
こうした管理職は、周囲が何も言えない空気もつくり出してしまいます。
➁「自分はこうやって育てられた」という固定観念が強い
「厳しさを乗り越えてこそ成長する」「昔の厳しさはこんなものではなかった」など、指導には厳しさが欠かせないと考えています。したがって、時に感情的な叱責や威圧的な態度も必要だと考えています。そして、(心身が)弱いのは本人のせいだとも思うのです。
「厳しく指導してもちゃんとついてくる部下もいる」「組織のため、会社のために必要な仕事をしているのだ」「厳しく指導するのは愛のムチと一緒だ」などの思いが口をついて出てきます。
共通しているのは、時代の変化を受け入れることができない、変化を理解できないことのようです。それだけ変わるということの難しさの一面を示しているとも言えなくはありませんが。
そして、パワハラの当事者になって聞く言葉の代表が「そんなつもりではなかった」「私は正しいと思って指導していた」などです。変われないのでしょうか? 否、変わろうとしないのだと言わざるを得ません。
研修的視点に立てば、パワハラ行為によって発生させるリスクというものをしっかりと考えてみるべきという視点が必要になってくるでしょう。
関連するカテゴリーの記事
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)③
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)②
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)①
- 10.管理職として機能しているか⑤
- 10.管理職として機能しているか④
- 10.管理職として機能しているか③
- 10.管理職として機能しているか②
- 10.管理職として機能しているか①
- 9.管理職のリーダーシップ⑤
- 9.管理職のリーダーシップ④
- 9.管理職のリーダーシップ③
- 9.管理職のリーダーシップ②
- 9.管理職のリーダーシップ①
- 8.管理職のオンラインマネジメント
- 7.管理職のチームづくり④
- 7.管理職のチームづくり③
- 7.管理職のチームづくり②
- 7.管理職のチームづくり①
- 6.管理職の部下育成③(管理職の部下育成(OFF・JTや自己啓発での能力アップを後押しする)
- 6.管理職の部下育成②(権限を委譲する)
- 6.管理職の部下育成①(部下育成の二つの方向性)
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑦
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑥
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑤
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め④
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め③
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め②
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め①
- 4.管理職の方針管理と日常管理
- 3.管理職の戦略思考
- 2.管理職の座標軸(役割コンセプト)とは何か②
- 2.管理職の座標軸(役割コンセプト)とは何か①
- 1.管理職の意思決定②(意思決定のための基本原則)
- 1.管理職の意思決定①(意思決定できない5つの理由)