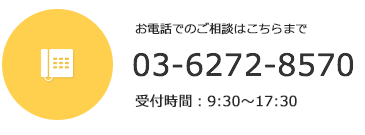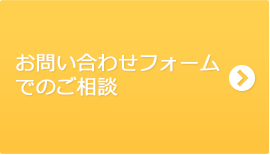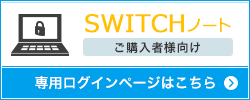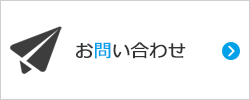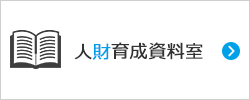HOME » 人財育成資料室 » 管理職実践講座 » 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)②
11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)②
2.部下や周囲からパワハラと言われると、管理職は落ち込む
「それはパワハラでは…」と言われて、それ以来、何も言えなくなった(何も言わなくなった)管理職はかなりいるようです。これでは管理職としての役割・責任を果たすことはできないのですが、心理的なショックはかなり大きく、さまざまな感情に陥ることが多いようです。
・最初は「困惑」
「え!パワハラ?」「指導の仕方はいつもと変わらないのに」「時に強く言うことはあるが、パワハラと言われるほどではないはず」「いったいどこが悪かったのだろうか」
→何がパワハラに該当するのかがわからない段階でしょう。
・次に「反発」
「指導場面で多少強く言わなければならないのは必要なこと」「部下のためを思って指導しているのに、パワハラと受け止められてしまうとは納得いかない」「私の指導をパワハラと言われるのであれば何も言えなくなってしまう」
→部下の側が過剰に反応してしまっているのではないか、私の責任ではないという反発心が生まれます。
・そして「動揺」
「このままでは管理職である自分に非があると言われてしまう」「自分の持論を言えば言うほど問題視されてしまう」「明確な理論武装ができていなくて、関係者を説得できそうにない」
→管理職としての信頼喪失や評価ダウンにつながるという不安が増幅してきます。
・最後に「無力感」
「組織のために、部下のために頑張ってきたのにそれが通用しなくなった」「もう管理職としての自信が持てない」「これからは、何を言ってもパワハラ扱いされるかもしれない」「もう部下に何も言わない方がいいのかも…」
→今後も部下との関わりを持ちながらマネジメントしていく気力をなくしてしまいます。
こうした問題を抱えている管理職の姿、さらにはこうした状況を見聞きしていることから、自分の擁護策として“何もしない”という対応の在り方が増加傾向にあるのです。
研修的視点に立てば、パワハラに関する「パワハラ原則の理解と現場で遭遇しているケースの判断基準を養う」「疑問や悩みを顕在化し、共有化を促進する」などが予防策支援としてあるでしょう。
関連するカテゴリーの記事
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)③
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)②
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)①
- 10.管理職として機能しているか⑤
- 10.管理職として機能しているか④
- 10.管理職として機能しているか③
- 10.管理職として機能しているか②
- 10.管理職として機能しているか①
- 9.管理職のリーダーシップ⑤
- 9.管理職のリーダーシップ④
- 9.管理職のリーダーシップ③
- 9.管理職のリーダーシップ②
- 9.管理職のリーダーシップ①
- 8.管理職のオンラインマネジメント
- 7.管理職のチームづくり④
- 7.管理職のチームづくり③
- 7.管理職のチームづくり②
- 7.管理職のチームづくり①
- 6.管理職の部下育成③(管理職の部下育成(OFF・JTや自己啓発での能力アップを後押しする)
- 6.管理職の部下育成②(権限を委譲する)
- 6.管理職の部下育成①(部下育成の二つの方向性)
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑦
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑥
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑤
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め④
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め③
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め②
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め①
- 4.管理職の方針管理と日常管理
- 3.管理職の戦略思考
- 2.管理職の座標軸(役割コンセプト)とは何か②
- 2.管理職の座標軸(役割コンセプト)とは何か①
- 1.管理職の意思決定②(意思決定のための基本原則)
- 1.管理職の意思決定①(意思決定できない5つの理由)