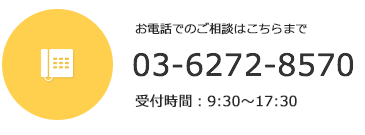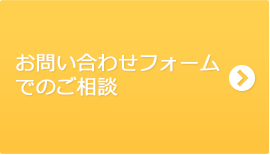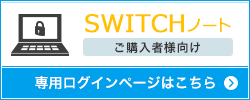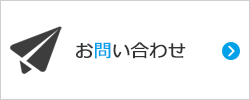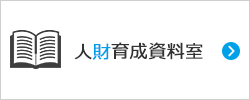HOME » 人財育成資料室 » 管理職実践講座 » 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)①
11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)①
1.パワハラは減っていない!
2022年4月1日から中小企業にも義務付けられた「パワハラ防止対策」への取り組みですが、この原稿を書いている2025年4月で丸3年が経ちました。
職場のハラスメントに関する実態調査(厚生労働省、2024年3月)によりますと、パワハラ予防・解決の取り組みを実施していると答えた企業は95%に上ります。その中身は、パワハラに関してみれば、「相談窓口の設置と周知」(86%)が最も高く、「ハラスメントの内容、職場におけるハラスメントをなくす旨の方針の明確化と周知・啓発」(83%)、「相談したこと、事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益取り扱いをされない旨の定めと周知・啓発」(68%)など、対策としては進んできているようです。
しかし、こうした対策を講じてはいるものの、過去3年間でハラスメントの発生件数におけるパワハラの比率は64%に上っていること、さらに、過去3年間のパワハラの相談件数は(30%が変わらない、20%が増加している)減ってはいないのです。相談体制の拡充で水面下に潜んでいたものが顕在化していることは対策としては功を奏していると判断できますが、「周知・啓発」策は今ひとつというところなのかもしれません。
さらに、見逃してはならないのが、ハラスメント対策は適切に行われているか、ということです。実際にハラスメント対策に取り組む際には「ハラスメントかどうかの判断が難しい」と悩むケースは多くなっており、このことが「適切な判断と対応」を遅らせてしまっているようです。
従業員の側からすれば、「会社が、パワハラがあることは認識していた」(37%)、「会社がハラスメントの発生を知ったのに、特に何もしなかった」(53%)、「ハラスメントがあったともなかったとも判断せずあいまいなままだった」(61%)などと、会社側の対応に不満を持っている人が多くいます。
周知・啓発はしていても、発生時の適切な対応がなされているのはまだ少ないと言わざるを得ません。
これをハインリッヒの法則(労働災害の発生比率の説明として使われている法則。1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットがある)に例えるならば、今はまだ大きな問題になることなく済んでいるが、これを放置しておくといつか会社に損害を与えかねないほど大きな問題になる、ということでしょうか。
研修に関して言えば、弊社では2022年の上期(4月~9月)にはパワハラ防止セミナーや研修のお問い合わせを多くいただきました。残念ながらその何割かは「対策を講じていますというポーズを示すためのもの」でした。3年前に一度手立てを講じたから終わりではなく、認知・周知度が高まるほどに問題が顕在化してくると考えた方がいいのではないでしょうか。そして、現場でくすぶっている問題の火消しのためには、やはり一歩踏み込んだ教育もまた必要だと感じています。
関連するカテゴリーの記事
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)②
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)①
- 10.管理職として機能しているか⑤
- 10.管理職として機能しているか④
- 10.管理職として機能しているか③
- 10.管理職として機能しているか②
- 10.管理職として機能しているか①
- 9.管理職のリーダーシップ⑤
- 9.管理職のリーダーシップ④
- 9.管理職のリーダーシップ③
- 9.管理職のリーダーシップ②
- 9.管理職のリーダーシップ①
- 8.管理職のオンラインマネジメント
- 7.管理職のチームづくり④
- 7.管理職のチームづくり③
- 7.管理職のチームづくり②
- 7.管理職のチームづくり①
- 6.管理職の部下育成③(管理職の部下育成(OFF・JTや自己啓発での能力アップを後押しする)
- 6.管理職の部下育成②(権限を委譲する)
- 6.管理職の部下育成①(部下育成の二つの方向性)
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑦
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑥
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑤
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め④
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め③
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め②
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め①
- 4.管理職の方針管理と日常管理
- 3.管理職の戦略思考
- 2.管理職の座標軸(役割コンセプト)とは何か②
- 2.管理職の座標軸(役割コンセプト)とは何か①
- 1.管理職の意思決定②(意思決定のための基本原則)
- 1.管理職の意思決定①(意思決定できない5つの理由)