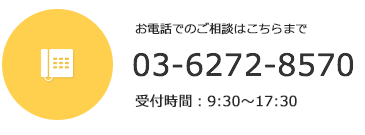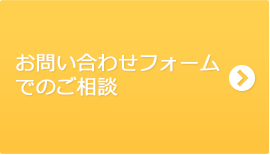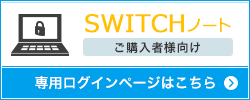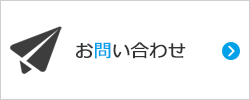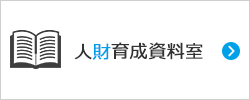HOME » 人財育成資料室 » 管理職実践講座 » 3.管理職の戦略思考
3.管理職の戦略思考
戦略思考とは「目標を達成するための最善策(具体的な道筋)を考える思考法である」ということができます。
目標達成のための最善策を考えるとなると、3つの重要なキーワードが出てきます。「目標」「仮説」そして「戦略」です。
目標は目指すべき姿、あるべき姿のことです。
戦略は目標を達成するための具体的な道筋です。この戦略は科学的、論理的考察し立案しなければなりません。
目標の達成に影響を及ぼす諸要素(環境の変化、顧客の変化など)が複雑になればなるほど、目標と戦略を結ぶ「仮説」が重要になってきます。
実は戦略の立案には、この仮説が重要な役割を果たしているのです。戦略思考の要は仮説思考にあるといっても良いでしょう。
営業の世界で今も言われていることが、「営業は経験・勘・度胸が必要だ」とか「根性が必要だ」ということです。さすがに近年はこれだけではだめで、営業を科学する力が必要だと言われていますが、営業の世界における「戦略」となると「?」が付くケースが未だに多いのです。この現象は実は営業だけに限ったことではありません。非営業分野においても現在のビジネス環境を押さえた戦略の立案力には弱さが目立ちます。
その一番の要因が「仮説」を立てることができず、過去の経験に基づいて判断しているということです。ですから結局は経験と勘なのです。そして、こうした経験思考が強くなりすぎ、仮説を立てるにも、何をどうしていいか分からないという管理職が増加傾向にあるのも事実なのです。
管理職自身は気づいていないのですが、戦略が明確でないと打ち出す方針や施策が、部下からは
①何を目指してどう頑張るのかをはっきり言ってくれない
②どこを重点化するのか、何を優先するのかが不明
③説明抜きでいきなり目標や作業指示がおりてくる
と受けとめられてしまい、
・思い付きとその場限りの施策だ
・何でもありの総花的な施策だ
・根性論でただがんばれといっているだけだ
と判断されてしまっているのです。
これでは、管理職としてのマネジメントは機能しません。
繰り返しになりますが、管理職として戦略を立案する際のポイントを見ていきましょう。
まず、目標の設定です。
戦略の立案は、目標からスタートします。戦略は目標を達成するための道筋を立てることです。ですからこの目標が曖昧なままではスタートできません。
そして、良い仮説を立てるためには、
①「ビジネス環境に対する認識と情報の収集」、つまりビジネスの現場の情報を的確につかむことが前提になります。経済や市場環境の動向を把握し、その中での可能性や制約条件を知ることが大変重要なのです。
②戦略を実行できる組織の力が必要になります。つまり組織力の強みと弱みを把握しておかなければなりません。
③そうして、「Aという方法をとるとどうなるか」「Bという方法をとるとどうなるか」の前提となる条件を設定することが戦略立案のスタートになります。
次に、仮説を元に、戦略を立てることです。
戦略を立案するためのフレームワークがあります。PEST分析、ファイブフォース、SWOT分析、3C分析、5C分析、4Pのマーケティングミックスなどの活用が有効です。これは営業以外でも十分活用できます。
良い戦略を立案するためには
仮説思考が持てているか
仮説の精度を高めるために普段から必要情報を収集しているか
が重要で、戦略の立案が必要な場面に直面してから慌てて情報収集→仮説→戦略をたてるようなやり方で上手くいったためしはありません。
最後に押さえておかなければならないことは、前提としている条件が変われば戦略も変わるということです。
前提条件は変わる→だから前提条件としている要素(情報)の変化を見続けていく必要がある→そして前提条件の変化にダイナミックに対応していくことが求められているのです。
関連するカテゴリーの記事
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)②
- 11.パワーハラスメント対策(ノンパワハラ・マネジメントのその後、そして今)①
- 10.管理職として機能しているか⑤
- 10.管理職として機能しているか④
- 10.管理職として機能しているか③
- 10.管理職として機能しているか②
- 10.管理職として機能しているか①
- 9.管理職のリーダーシップ⑤
- 9.管理職のリーダーシップ④
- 9.管理職のリーダーシップ③
- 9.管理職のリーダーシップ②
- 9.管理職のリーダーシップ①
- 8.管理職のオンラインマネジメント
- 7.管理職のチームづくり④
- 7.管理職のチームづくり③
- 7.管理職のチームづくり②
- 7.管理職のチームづくり①
- 6.管理職の部下育成③(管理職の部下育成(OFF・JTや自己啓発での能力アップを後押しする)
- 6.管理職の部下育成②(権限を委譲する)
- 6.管理職の部下育成①(部下育成の二つの方向性)
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑦
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑥
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め⑤
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め④
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め③
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め②
- 5.ノンパワハラ・マネジメントの勧め①
- 4.管理職の方針管理と日常管理
- 3.管理職の戦略思考
- 2.管理職の座標軸(役割コンセプト)とは何か②
- 2.管理職の座標軸(役割コンセプト)とは何か①
- 1.管理職の意思決定②(意思決定のための基本原則)
- 1.管理職の意思決定①(意思決定できない5つの理由)